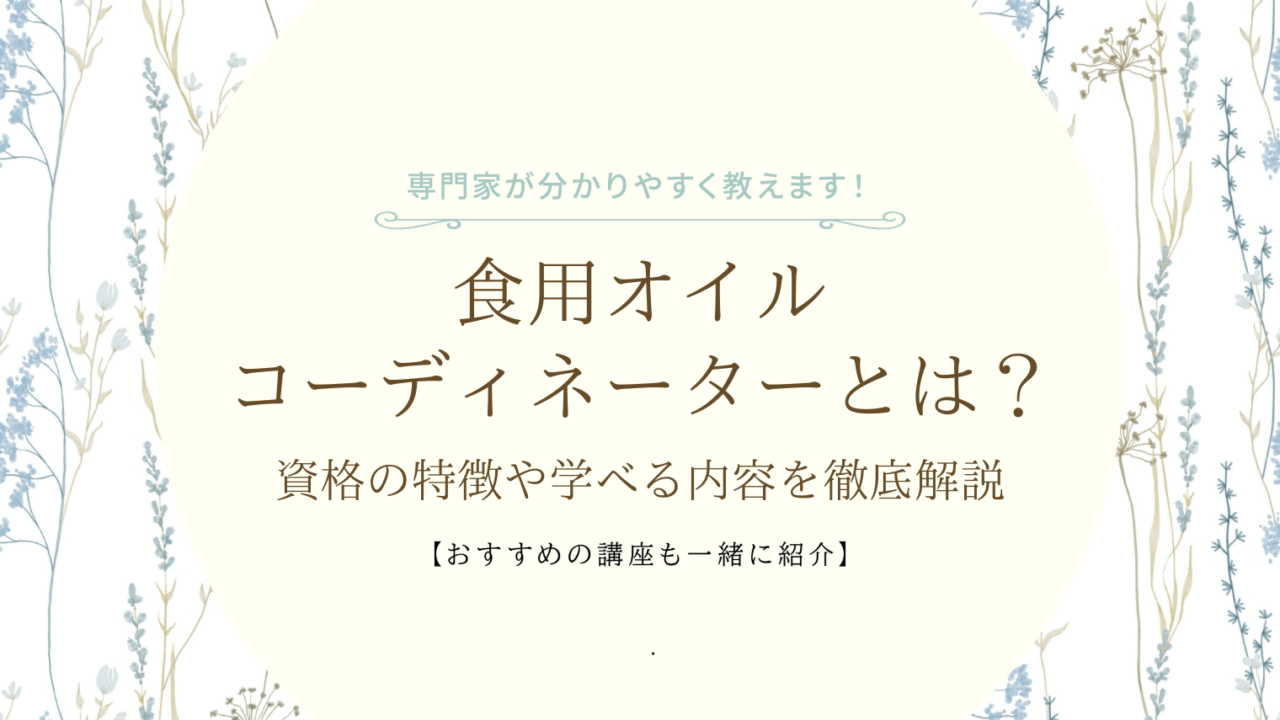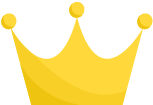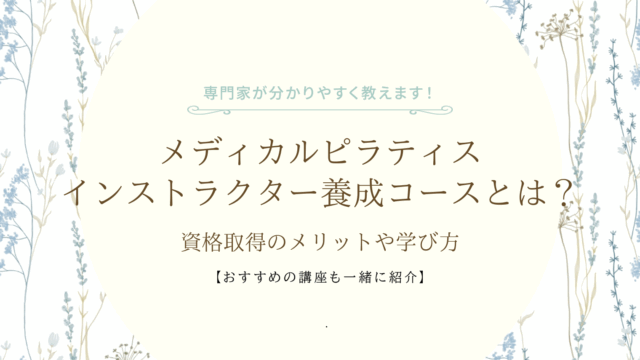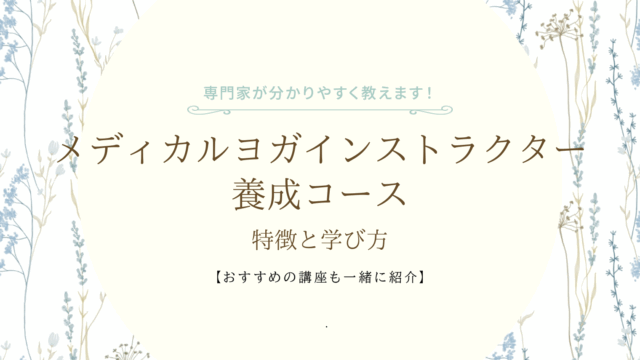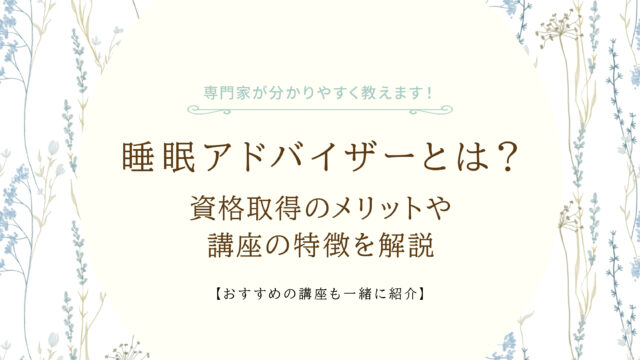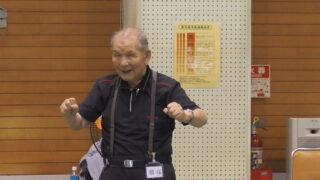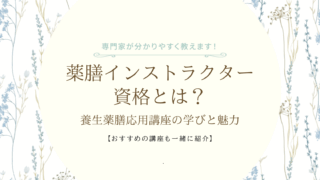近年、オリーブオイルやえごま油など「体に良い油」が注目されていますが、正しい知識を持って選べている人は意外と少ないのが現状です。
油の種類や使い方を誤ると、健康維持どころか生活習慣病のリスクを高めることもあります。
そこで役立つのが、日本統合医学協会が認定する「食用オイルコーディネーター資格」です。
本記事では、資格の特徴や学べる内容、取得方法から活かし方までを徹底解説し、油の専門知識を身につけたい方に役立つ情報をお届けします。
食資格は多くの種類が存在します。
この記事では特定非営利活動法人の日本統合医学協会が認定している「食用オイルコーディネーター資格」について解説しています。
\この記事をお読みの方におすすめの資格!/

脂質の基礎知識から油脂の種類、症状別の油の選び方、オイル別の料理への応用法、さらに調味料についても学べます。脂質は健康維持に重要な要素であり、正しい知識を身につけることで、自分や家族の食生活の改善、健康管理に役立てることができます。
また、セルフメディケーションや健康指導にも役立つスキルを身につけることができます。
発酵食品の基礎知識から甘酒、ぬか床、納豆、麹を使った調味料など、それぞれの発酵食品の特性や作り方、健康効果を学びます。さらに、ご家庭で実践できる発酵食品を使ったレシピも紹介されており、日常生活にすぐに取り入れることができます。
東洋医学に基づき、自身の体質や健康状態を把握する方法を学び、季節ごとに適した食材を使ったレシピを紹介します。無理なく続けられる「ちょこっとおかず」レシピも充実しており、毎日の食事に薬膳を自然に取り入れることが可能です。この講座を通じて、家族や自分の健康をサポートし、予防医学としての薬膳の力を身につけてみませんか?
食用オイルコーディネーターとは?

食用オイルコーディネーターは、特定非営利活動法人 日本統合医学協会が発行する資格で、油の種類や成分、健康効果、調理法まで体系的に学べる専門資格です。
サラダ油やオリーブオイル、えごま油など多様な油の特徴を正しく理解し、家庭や仕事での食生活改善に役立てられるのが特徴です。
日本統合医学協会が発行する資格の概要
日本統合医学協会は、医療・福祉・食・心理など多分野で専門資格を展開している団体です。
食用オイルコーディネーター資格はその一つで、「油の正しい知識を生活や健康維持に活かす」点に特化しています。
受講はオンライン完結型で、基礎理論から応用まで段階的に学べ、修了後には協会認定資格として社会的な信頼を得られるのが特徴です。
他団体資格との違いと注意点
食に関する資格には、栄養学や薬膳、オーガニック関連など複数の団体が発行するものがあります。
しかし「食用オイルコーディネーター」は、日本統合医学協会が認定する油に特化した唯一の資格です。
他団体の講座ではオイルが部分的に扱われる場合がありますが、本資格は種類や調理法、健康効果までを専門的に網羅している点が大きな違いです。
受講を検討する際は、資格名や発行団体を混同しないよう注意しましょう。
なぜ今「食用オイル」が注目されているのか

近年、健康志向の高まりとともに「油の選び方」が大きな関心を集めています。
オリーブオイルやえごま油、ココナッツオイルなどはメディアでも頻繁に取り上げられ、生活習慣病予防や美容効果との関連が注目されるようになりました。
一方で、安価な精製油の過剰摂取や酸化した油の使用は健康リスクにつながることもあり、正しい知識を持つことが重要です。
そのため、油を科学的に理解し、日常生活に役立てる専門人材の育成が求められています。
健康長寿や美容との関係
食用オイルは単なる調理用の油ではなく、体の健康維持に深く関わっています。
- えごま油・亜麻仁油:オメガ3脂肪酸が血流改善や認知症予防に有効
- オリーブオイル:抗酸化成分が豊富で、老化防止や美肌に効果的
- ココナッツオイル:中鎖脂肪酸がエネルギー代謝を助ける
適切な種類のオイルをバランスよく摂取することは、生活習慣病の予防だけでなく、若々しい体と美しさを保つ鍵となります。
現代の食生活で起こりやすい課題
- 加工食品や外食による安価な油の過剰摂取
- オメガ6脂肪酸の偏りによる炎症リスク
- 酸化した油を無意識に摂取する機会の多さ
- 調理法を誤ることで「良い油」も逆効果になる可能性
こうした問題を避けるために、正しい知識を持つことが、健康維持には欠かせません。
食用オイルコーディネーター資格で学べる内容

食用オイルコーディネーター資格では、普段の生活で見落としがちな「油の正しい知識」を体系的に学びます。
具体的には、飽和脂肪酸や不飽和脂肪酸の違い、オメガ3・6・9の特徴と働き、酸化や加熱に強い油の見分け方など、健康と直結する基本知識が中心です。
さらに、料理に合わせた使い分けや保存方法、栄養学的な効果までを幅広くカバーします。
これにより、単なる調理油の選び方にとどまらず、日常生活や健康管理に活かせる「実践的スキル」が身につきます。
基礎知識(種類・成分・効果)
食用オイルには多くの種類があり、それぞれに含まれる成分や健康効果が異なります。
代表的な「オリーブオイル」にはオレイン酸が豊富で、血中コレステロールのバランス改善に役立ちます。
「えごま油」や「亜麻仁油」にはオメガ3脂肪酸が多く含まれ、脳や心臓の健康維持に効果的です。
一方で「ココナッツオイル」は中鎖脂肪酸を多く含み、エネルギー代謝を高めやすいのが特徴です。
このように、油の種類ごとの特性を理解することは、健康維持や美容の実践に直結します。
活用法(調理・健康管理・ライフスタイル提案)
食用オイルの正しい活用法を知ることで、日常の食生活は大きく変わります。
加熱調理には酸化しにくいオリーブオイルやキャノーラ油が適しており、サラダや冷菜には熱に弱いえごま油や亜麻仁油を使うのが理想です。
さらに、摂取量をコントロールしながら複数のオイルを組み合わせることで、脂肪酸のバランスを整えることができます。
ライフスタイル面では、ダイエットやアンチエイジング、家族の健康管理など目的に合わせたオイルの選択が可能になります。
資格取得の流れと学び方

食用オイルコーディネーター資格は、申し込みから学習、そして資格認定までをすべて自宅で完結できる点が大きな特徴です。
学習期間の目安は1〜3か月で、最大3か月間の受講が可能です。
忙しい方でも、期間延長手続きを行えば学習を継続できる仕組みが整っています。
全体の流れは「教材を使ったオンライン学習 → 修了試験 → 資格申請・入会手続き → 認定証発行」というシンプルなものです。
受講方法(オンライン学習・教材内容)
食用オイルコーディネーター資格は、完全オンラインで学べる仕組みになっています。
受講申し込み後は、自宅にテキストや教材が届き、パソコンやスマートフォンを活用しながら学習を進めます。
教材には、油の種類や成分、健康効果、調理や保存の注意点などが体系的にまとめられており、初心者でも理解しやすい内容です。
通学の必要がないため、全国どこからでも自分のペースで取り組めるのが大きなメリットです。
修了から資格認定までの手順
学習を終えた後は、オンライン形式で実施される修了試験を受験します。
試験は自宅から受けられるため、安心して取り組むことができます。
内容はテキストで学んだ基礎から応用まで幅広く出題され、合格基準を満たすと次のステップへ進みます。
合格後は、日本統合医学協会への資格申請と入会手続きを行うことで、正式に「食用オイルコーディネーター」として認定され、認定証が発行されます。
この流れにより、学んだ知識を社会的に証明できます。
どんな人におすすめの資格か

食用オイルコーディネーター資格は、食や健康に関心を持ち、正しい知識を生活や仕事に役立てたい人に適しています。
特に「家族の健康を守りたい主婦・主夫」「美容やアンチエイジングを意識する方」「食育や栄養に関わる職種の人」におすすめです。
また、飲食業界や健康関連の仕事をしている人にとっても、専門性を高めて信頼を得る武器になります。
家庭での健康管理を意識したい人
毎日の料理で使う油は、家族の健康状態に直結します。
食用オイルコーディネーター資格では、どの油が血管や脳の健康維持に役立つか、どの油が加熱に適しているかといった知識を得られるため、家庭の食事改善にすぐ活かせます。
子どもの発育期や高齢の家族の健康管理など、ライフステージに合わせた油の選び方ができるようになるのが大きな強みです。
安心でバランスの取れた食生活を整えたい家庭に特に適した資格です。
専門職・キャリアアップを目指す人
飲食業界や栄養指導、健康関連の分野で働く人にとって、油の専門知識は信頼を高める大きな武器となります。
例えば、飲食店では料理に適したオイルを提案でき、栄養士や介護職では生活習慣病予防や高齢者の健康維持に役立てられます。
また、美容やフィットネスの分野でも、アンチエイジングや体づくりに効果的な油の活用法を伝えられるようになります。
資格取得は専門性を補強し、キャリアアップや差別化につながる大きなステップです。
食用オイルコーディネーターの活かし方
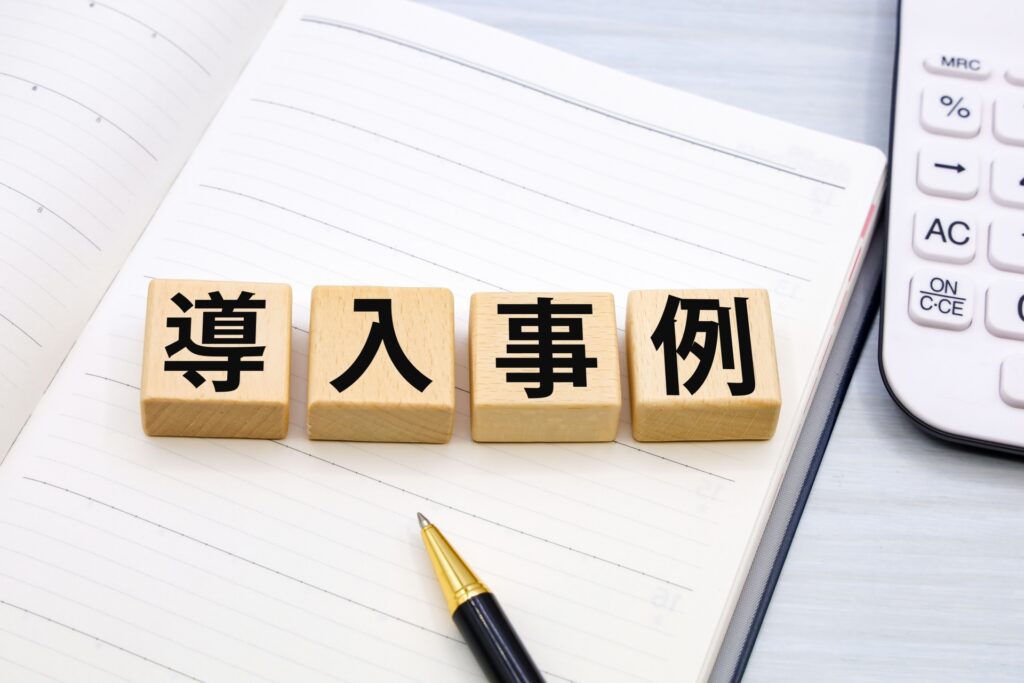
食用オイルコーディネーターの知識は、日常の食卓だけでなく、学んだことを社会に広げる形でも活用できます。
例えば、地域の健康講座や料理教室で「油の正しい使い方」を伝える活動、ブログやSNSでの情報発信などは、多くの人に役立つ実践方法です。
また、商品開発やメニュー監修の場面で「油の専門家」として意見を取り入れてもらえる機会もあります。
このように資格取得は、自分や家族のためにとどまらず、社会的に健康意識を高める活動へつなげられる点が大きな魅力です。
日常生活や家族の健康への応用
食用オイルコーディネーター資格で得た知識は、日々の献立や調理法に直結します。
例えば、サラダには加熱に弱いえごま油を、炒め物には酸化に強いオリーブオイルを選ぶなど、適材適所で油を使い分けることで健康効果を高められます。
さらに、家族の年代や体調に合わせて油の種類を調整することで、成長期の子どもや生活習慣病が気になる高齢者にも安心な食事を提供できます。
こうした工夫は、家庭の健康寿命を延ばす大切なサポートになります。
仕事・発信活動・地域貢献での活用例
食用オイルコーディネーターの知識は、仕事や社会活動にも幅広く活かせます。
飲食業界では、料理に最適な油を提案することでメニューの価値を高められます。
栄養指導やセミナーでは、生活習慣病予防や健康管理の観点から「油の正しい選び方」を伝える専門家として信頼を得られます。
また、ブログやSNSでの発信を通じて健康情報を広めたり、地域の料理教室や講座で油の知識を共有することも可能です。
資格は社会的な貢献活動にもつながります。
食用オイルコーディネーターと他食系資格の違い
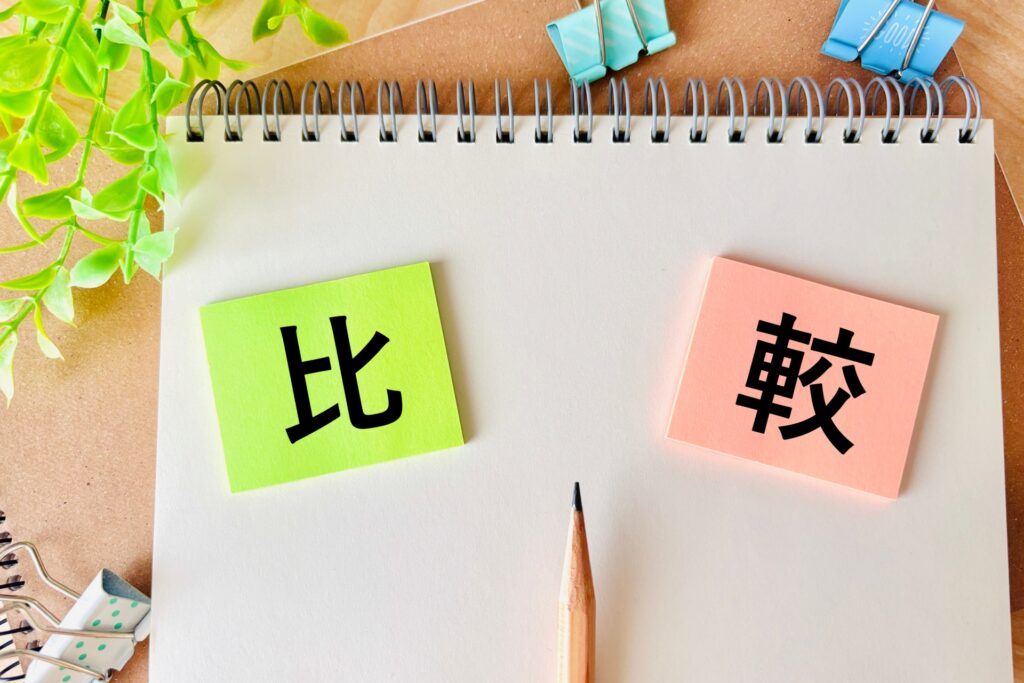
日本統合医学協会には「食」に関する資格は数多くありますが、それぞれ学べる範囲や目的が異なります。
食用オイルコーディネーターは油に特化した専門資格であり、発酵食美インストラクターや薬膳系資格、食生活健康長寿アドバイザーとは学ぶ切り口が異なります。
下記の表で違いを整理しました。
| 資格名 | 学ぶ対象 | 主な特徴 | 活かせる場面 |
|---|---|---|---|
| 食用オイルコーディネーター | 食用オイル全般(オリーブ油、えごま油、ココナッツ油など) | 油の種類・成分・健康効果・調理法に特化 | 家庭の食生活改善、飲食業界、健康指導、発信活動 |
| 発酵食美インストラクター | 発酵食品(味噌・納豆・麹など) | 発酵の仕組みや美容・健康効果を理解 | 食育活動、美容・健康分野での提案 |
| 薬膳インストラクター | 薬膳食材全般 | 東洋医学の考え方に基づき、体質や季節に応じた食材活用を学ぶ | 料理教室、健康相談、セルフケア |
| 薬膳検定1級・アーユルヴェーダスパイス検定1級 | 薬膳理論とスパイス | 薬膳の基本とアーユルヴェーダのスパイス活用を総合的に学ぶ | セルフケア、健康料理、発信活動 |
| 食生活健康長寿アドバイザー | 栄養学全般 | 健康寿命を延ばすための栄養学と生活習慣を体系的に学ぶ | 高齢者施設、福祉現場、家庭の食事管理 |
このように、食用オイルコーディネーターは「油の専門家」として位置づけられ、他資格と組み合わせることで食と健康に関する理解をさらに広げることが可能です。
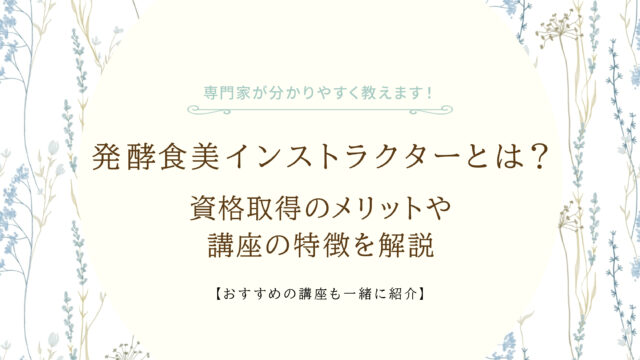
資格取得にかかる費用や期間

受講期間は最大3か月、平均1〜3か月で修了できます。受講料は以下の通りです。
- 一般受講料:39,600円(税込43,560円)
- モニター受講料:19,800円(税込21,780円)
(条件:400字以上のレポート提出+受講後アンケート回答)
受講料には教材とeラーニングが含まれており、追加費用は発生しません。
コストパフォーマンスと得られるメリット
食用オイルコーディネーター資格は、短期間で効率的に専門知識を習得できる点で投資価値の高い講座です。
学んだ内容は日々の食生活改善に直結し、さらに仕事や発信活動にも活かせるため、資格取得後の活用範囲が広いのが特徴です。
特に「油の専門家」としての信頼を得られることは、健康や栄養に関わる分野で大きな強みになります。
費用以上に実用性が高く、一生使える知識を得られる点で、非常にコストパフォーマンスの高い資格といえます。
まとめ|食用オイルコーディネーターで広がる学びと実践

食用オイルコーディネーター資格は、毎日の食事に欠かせない油を正しく理解し、健康維持や美容、生活習慣病予防に役立てられる実践的な学びを提供します。
短期間で体系的に知識を習得でき、家庭の食卓改善から専門職での活用、情報発信まで幅広く応用できる点が大きな魅力です。
油は誰もが毎日口にする身近な食材だからこそ、正しい知識を持つことが一生の財産となります。
資格取得を通じて、自分や家族、社会の健康づくりに活かしていきましょう。
監修者

谷口 順彦
特定非営利活動法人日本統合医学協会理事
総合学園JOTアカデミー理事長
\この記事をお読みの方におすすめの資格!/

脂質の基礎知識から油脂の種類、症状別の油の選び方、オイル別の料理への応用法、さらに調味料についても学べます。脂質は健康維持に重要な要素であり、正しい知識を身につけることで、自分や家族の食生活の改善、健康管理に役立てることができます。
また、セルフメディケーションや健康指導にも役立つスキルを身につけることができます。
発酵食品の基礎知識から甘酒、ぬか床、納豆、麹を使った調味料など、それぞれの発酵食品の特性や作り方、健康効果を学びます。さらに、ご家庭で実践できる発酵食品を使ったレシピも紹介されており、日常生活にすぐに取り入れることができます。
東洋医学に基づき、自身の体質や健康状態を把握する方法を学び、季節ごとに適した食材を使ったレシピを紹介します。無理なく続けられる「ちょこっとおかず」レシピも充実しており、毎日の食事に薬膳を自然に取り入れることが可能です。この講座を通じて、家族や自分の健康をサポートし、予防医学としての薬膳の力を身につけてみませんか?