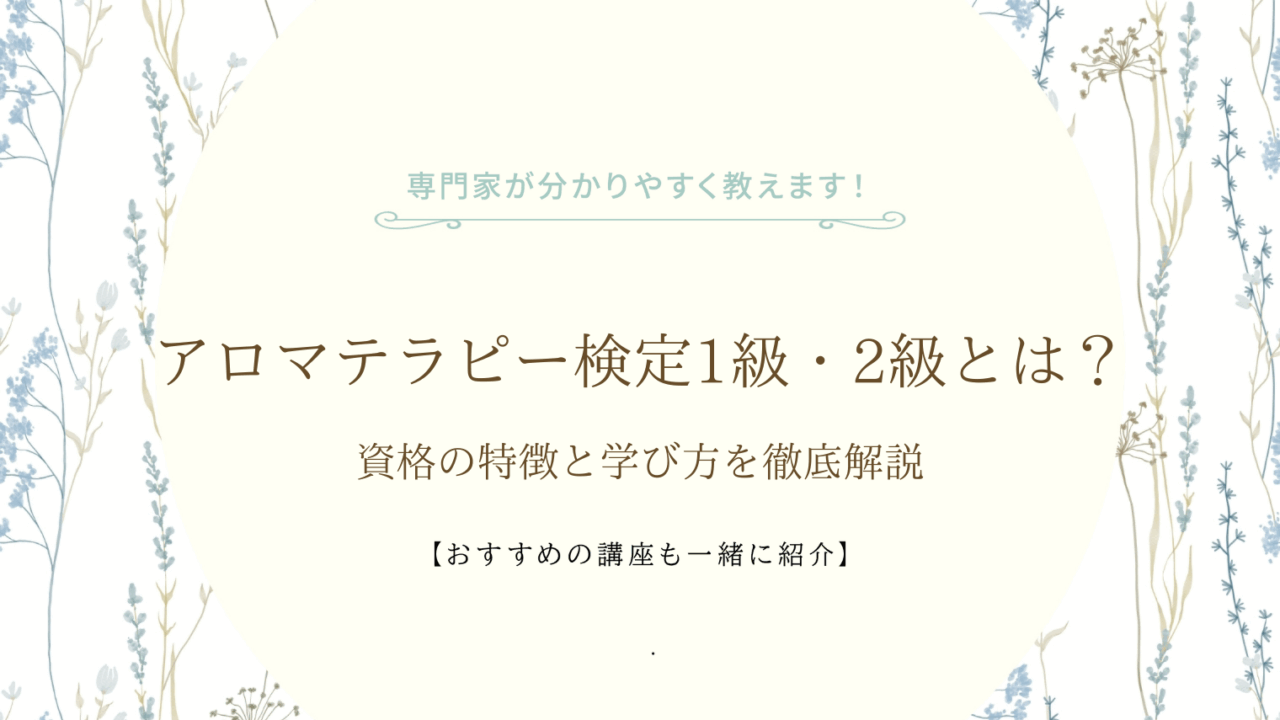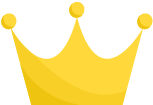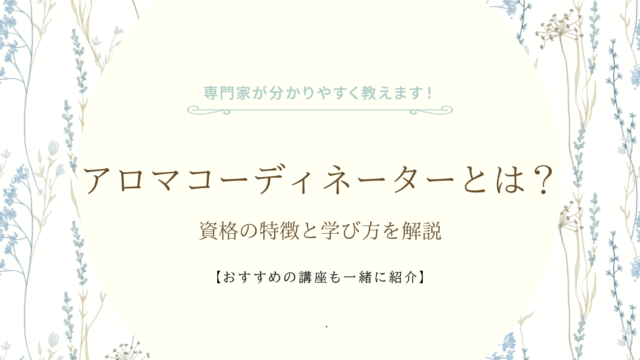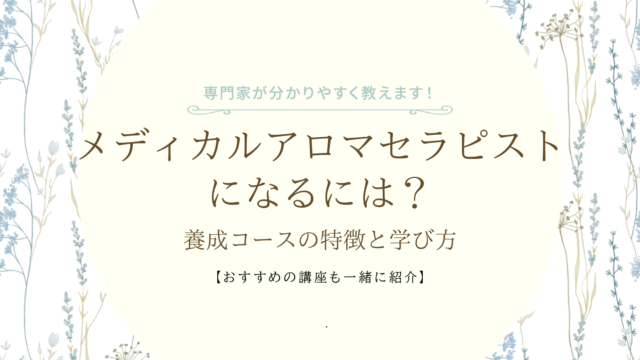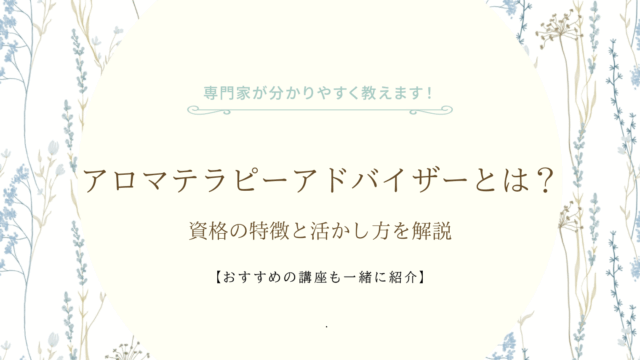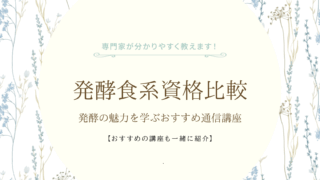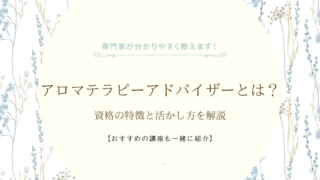アロマテラピー検定1級・2級は、日本アロマ環境協会(AEAJ)が実施する、香りの正しい知識と安全な使い方を学べる公式資格です。
アロマ初心者の入門資格として人気が高く、精油の基礎から生活への取り入れ方まで体系的に身につけられます。
本記事では、アロマテラピー検定1級・2級の違いや出題範囲、試験概要、学び方、合格後のステップアップまでを徹底解説。
さらに、他団体資格との違いやAEAJ資格の信頼性についても詳しく紹介します。
これから受験を検討している方はもちろん、アロマを生活や仕事に活かしたい方にも役立つ内容です。
香りのある暮らしを楽しみたい方も、将来的にアロマを仕事に活かしたい方も。
アロマテラピー検定は、誰でも安心して始められる第一歩です。
この記事を読んで、あなたに合った学び方を見つけてみましょう。
\この記事をお読みの方におすすめの資格!/

心と体の状態に合わせた精油のブレンディングなど、メディカルアロマの活用法を教授できる能力を認定する資格です。
メディカルアロマのスペシャリストとして、精油の専門知識だけでなく基礎医学や心理学など幅広い知識を習得し、目的に合わせた利用法を指導できる専門人材になることを目的にしています。
医療や福祉の現場でアロマセラピーの知識と技術を活かすことを目指します。精油が心身に及ぼす効果を深く学び、対象者や目的に応じた適切なアロマの使用法を身に付けることで、医療現場での代替療法や疾病予防、健康増進に役立てられます。クリニカルアロマセラピーは、西洋医学の補完的な役割を担い、統合医療としても注目されています。
身体の仕組みや心理学、ハーブの知識を基に、アロマが心と体に与える影響を理解することを目指します。精油の特性を学び、医学的視点でのアロマセラピーを通じて、不調に対応するトリートメント技術を習得します。
医療現場でも活用できる高度な知識と技術を持ったセラピストを育成します。
アロマテラピー検定とは?日本アロマ環境協会(AEAJ)が発行する公式資格

日本アロマ環境協会(AEAJ)より引用
「アロマテラピー検定」は、日本アロマ環境協会(AEAJ)が実施する、アロマの正しい知識と安全な活用方法を学ぶための公式資格です。
精油の基本的な使い方から、香りが心身に与える作用、暮らしへの取り入れ方までを体系的に学べる内容になっています。
主な特徴は以下の通りです。
- 公益社団法人が運営する信頼性の高い検定制度
- 初心者でも安心して挑戦できる構成(2級→1級の順に段階的学習)
- 学んだ知識は、日常生活・美容・介護・教育など多分野で活用可能
アロマを初めて学ぶ方が、香りを安全に楽しむ第一歩として最適な資格です。
検定の目的と学べる内容
アロマテラピー検定の目的は、香りを安全かつ効果的に生活へ取り入れられる人を育成することにあります。
単に精油の知識を覚えるだけでなく、心と体の健康維持、環境づくり、そしてストレスケアなど、日常生活の質を高める実践的な内容が学べます。
学習内容の一例は以下の通りです。
- 各精油(エッセンシャルオイル)の特徴と作用
- ブレンドや芳香浴など、香りの使い方
- 嗅覚と脳・自律神経の関係
- 安全な使用方法と注意点
- 暮らしの中でのアロマ活用(掃除・美容・睡眠など)
アロマテラピーを「感覚的な癒し」から「根拠あるセルフケア」へと広げるための基礎を学べる検定です。
AEAJ(日本アロマ環境協会)の概要と信頼性
日本アロマ環境協会(AEAJ)は、日本で最も公的性格の強いアロマテラピー関連団体です。
内閣総理大臣所轄の公益社団法人として、アロマの正しい知識の普及と人々の健康的な生活環境づくりを目的に活動しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 公益社団法人 日本アロマ環境協会 (Aroma Environment Association of Japan/AEAJ) |
| 設立 | 2005年4月1日 (前身団体は1996年設立) |
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前6丁目34番24号 AEAJグリーンテラス |
| 会員数(2025年3月時点) | 個人正会員:41,921名 法人正会員:237社 (登録会員1,562名) |
| 資格取得者数(累計) | 約50万人 (うちアロマテラピー検定合格者137,569名) |
| 認定スクール・教室 | 認定校125校・認定教室584教室 (全国展開) |
| 認定精油ブランド | 81ブランド (64社) |
| 所轄行政庁 | 内閣総理大臣 |
| 主な交流団体 | におい・かおり環境協会 日本エステティック協会 IFA、IFPA など |
AEAJは教育・研究・資格認定を通じて、アロマ業界の発展と信頼向上に寄与しています。
公益社団法人としての透明な運営により、日本国内で最も信頼されるアロマ資格発行機関といえるでしょう。
アロマテラピー検定1級・2級の違いと試験概要

アロマテラピー検定は、日本アロマ環境協会(AEAJ)が主催する、香りの正しい知識を段階的に学べる検定制度です。
2級では基礎的な精油の知識と生活への取り入れ方を、1級では心身のメカニズムや法的知識など、より深い理解と応用力を養います。
試験は年2回(5月・11月)に実施され、現在はインターネットを利用したオンライン試験(在宅)形式です。
特別な受験資格はなく、年齢や経験を問わず誰でも受験可能です。
出題範囲とレベルの違い
アロマテラピー検定の出題は、AEAJが発行する『アロマテラピー検定 公式テキスト(2020年6月改訂版)』から出題されます。
級ごとに学ぶ目的・範囲・対象精油が明確に異なります。
| 項目 | 2級 | 1級 |
|---|---|---|
| 学習目的 | アロマを安全に生活へ取り入れるための基礎知識 | 精油を目的に応じて使い分け、心身に活かす応用知識 |
| 出題数 | 55問 | 70問 |
| 精油の範囲 | 11種類 | 30種類 (2級の精油+19種類) |
| 主な出題分野 | アロマの基本 精油の特徴 安全性、実践法 | 上記+メカニズム ビューティ&ヘルスケア 法律、歴史 |
| 難易度 | 初心者向け(入門) | 中級者向け(応用) |
2級対象精油(11種)
スイートオレンジ/ゼラニウム/ティートリー/フランキンセンス/ペパーミント/ユーカリ/ラベンダー/レモン/ローズ(アブソリュート)/ローズオットー/ローズマリー
1級追加精油(19種)
イランイラン/クラリセージ/グレープフルーツ/サイプレス/サンダルウッド/ジャーマンカモミール/ジャスミン(アブソリュート)/ジュニパーベリー/スイートマージョラム/ネロリ/パチュリ/ブラックペッパー/ベチバー/ベルガモット/ベンゾイン(レジノイド)/ミルラ/メリッサ/レモングラス/ローマンカモミール
1級は2級の発展版として位置づけられていますが、どちらの級からでも受験可能です。
試験日・受験形式・受験料・合格基準
アロマテラピー検定は、年に2回(5月・11月頃)に実施される全国共通試験です。
すべての試験がオンライン(在宅)形式で行われるため、パソコンやスマートフォンがあれば全国どこからでも受験できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施時期 | 年2回(5月・11月頃) |
| 受験方法 | インターネット試験 (在宅受験・選択式) |
| 試験時間 | 2級:約30分 1級:約35分 |
| 受験資格 | 年齢・性別・経験不問 (どなたでも受験可能) |
| 出題数 | 2級:55問 1級:70問 |
| 受験料(税込) | 各級 6,600円 1級・2級併願 13,200円 |
| 合格基準 | 正答率80%以上 (得点開示なし) |
| 合格通知・認定証 | 試験後に合否通知、後日認定証が送付される |
試験は「アロマテラピー検定公式テキスト(2020年改訂版)」に基づいて出題され、マークシート方式の選択問題です。
受験環境は静かな個室が推奨され、通信回線は安定したWi-Fiまたはモバイル回線を使用します。
アロマテラピー検定が注目される理由と活かせる分野

近年、アロマテラピー検定が注目されているのは、「こころとからだの健康を自分で守る時代」に移り変わっているためです。
ストレス社会の中で、医療や薬だけに頼らず、日常の中で気分を整えたり、睡眠の質を高めたりするセルフケアの需要が高まっています。
アロマテラピー検定では、香りが人の心身に与える作用を「科学的な視点」で理解できるため、アロマを感覚的な癒しから根拠ある健康サポートへと発展させることが可能です。
こうした背景から、家庭や職場、福祉・教育現場など、幅広い領域で活用の場が広がっています。
ストレスケアやセルフケア需要の高まり
仕事・家庭・人間関係などによる慢性的な疲労感を抱える人が増え、「手軽にリラックスできる方法」を求める傾向が強まっています。
アロマテラピーは、嗅覚を通じて脳や自律神経に働きかけるため、短時間でも気分を切り替えたり、眠りの質を改善したりといった実感を得やすいセルフケア手段です。
アロマテラピー検定を学ぶことで、香りの心理的・生理的効果を理解し、自分や家族のストレスケアに活かすことができるようになります。

医療・介護・教育・美容など幅広い現場での活用
アロマの知識は、個人の癒しにとどまらず、職業分野での専門的な応用にも役立ちます。
- 医療・介護現場:香りによるリラクゼーションで患者や高齢者の不安を軽減
- 教育・福祉施設:子どもの情緒安定や学習環境の向上に貢献
- 美容・リラクゼーション業界:サロンの空間演出や施術の質向上に
- 企業・店舗:香りによる空間デザインやブランディングへの応用
このように、アロマテラピー検定で得た知識は、人と環境をより快適にするツールとして広く求められています。
効果的な学び方|合格を目指す勉強法とおすすめ教材

アロマテラピー検定は、独学でも通信講座でも学べる柔軟な試験です。
効率的に合格を目指すには、目的に合わせた学び方の選択が大切です。
学習の基本は、AEAJが発行する『アロマテラピー検定 公式テキスト(2020年改訂版)』。
このテキストから全問出題されるため、まずは内容を丁寧に読み込み、香りの特徴を覚えるところから始めます。
また、過去問題集や精油セットを使って実際に香りを嗅ぎながら学ぶことで、知識と感覚を結びつけるのがポイントです。
短期間で理解を深めたい方や体系的に学びたい方は、通信講座・オンラインスクールの利用もおすすめです。
講師による添削や香り教材のセットがつくため、効率的に学習を進められます。
独学での学習方法と活用しやすい教材
アロマテラピー検定は、独学でも十分に合格を目指せる資格です。
まずはAEAJ公式の『アロマテラピー検定 公式テキスト(2020年改訂版)』を中心に学びましょう。
このテキストは出題範囲をすべて網羅しており、基礎から応用まで体系的に学べます。
独学での学習ステップの一例:
- 公式テキストを1章ずつ読み進め、重要語句にマーカーを引く
- 精油の香りを実際に嗅ぎながら特徴を覚える
- 過去問題集・模擬問題で出題傾向を確認
- ノートを作り、精油の作用・禁忌事項を整理
おすすめ教材:
- AEAJ公式テキスト・問題集
- 精油セット(11種または30種)
- 精油プロフィール一覧(香りメモ付き)
香りを体験しながら学ぶことで、記憶に残る実感型の学習が可能です。
通信講座・スクールで体系的に学ぶ方法
短期間で効率よく合格を目指すなら、通信講座やスクールを利用した体系的な学習もおすすめです。
講座では、AEAJ公式テキストに沿ったカリキュラムに加え、講師による解説や香り教材がセットになっており、独学より理解を深めやすいのが特長です。
通信講座・スクール学習の主なメリット:
- 専任講師によるサポートで疑問をすぐに解消できる
- 香り教材や実習キット付きで、体験的に学べる
- 学習スケジュールが組まれており、継続しやすい
オンライン講座を活用すれば、自宅で自分のペースで学習でき、忙しい社会人や子育て中の方でも無理なく継続できます。
基礎をしっかり身につけたい方には、AEAJ認定スクールの受講が最も確実な方法です。
合格後のステップアップと資格の活かし方

アロマテラピー検定に合格すると、AEAJ認定資格への道が広がります。
まずは検定1級合格後に取得できる「アロマテラピーアドバイザー」で、学んだ知識を日常や仕事で実践的に活かすことができます。
その後は、自分の興味や目的に合わせて上位資格へ進み、「伝える・癒す・創る」といった専門分野へ発展可能です。
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザーへの進路
アロマテラピー検定1級合格者が最初に目指せるのが、アロマテラピーアドバイザー資格です。
この資格は、香りの安全な使い方や精油の基礎知識を他者に伝えることができる「実践的資格」として位置づけられています。
取得までの流れ:
- アロマテラピー検定1級に合格
- AEAJ個人正会員として入会
- 認定スクールで「アロマテラピーアドバイザー認定講習会」を受講
- 修了後、資格申請を行う
アドバイザー資格は、アロマの正しい使い方を普及・指導できる立場を得られる点が魅力です。
家庭や職場、地域講座などで活かせる信頼ある実務資格として、多くの検定合格者が次の一歩に選んでいます。
上位資格(インストラクター・ブレンドデザイナー等)との関係
アロマテラピーアドバイザーを取得した後は、さらに専門分野で活躍できる上位資格へ進むことが可能です。
目的に応じて学びを深めることで、教育・施術・デザインなど多方面でのキャリア形成につながります。
| 資格名 | 主な目的・特徴 |
|---|---|
| アロマテラピーインストラクター | 教育・講師としての指導スキルを習得。 アロマ教室やセミナーで活躍。 |
| アロマセラピスト | 実技を通じて心身のケアを行う専門職。 サロンや医療・福祉分野で需要が高い。 |
| アロマブレンドデザイナー | 香りのブレンド・空間演出を学び、ブランドや店舗の香り設計に応用。 |
| アロマハンドセラピスト | ハンドトリートメントを通じた癒しや交流を目的とした資格。 |
これらの資格は、アドバイザーで得た基礎知識を土台に、より専門的・実践的なキャリアへとつなげるステップアップ資格です。
他団体資格との違いとAEAJ資格の強み(比較・信頼性)

アロマテラピーに関する資格は、JAA(日本アロマコーディネーター協会)やIFA(国際アロマセラピスト連盟)など、複数の団体が発行しています。
その中で、日本アロマ環境協会(AEAJ)は、内閣総理大臣所轄の公益社団法人として唯一、非営利でアロマ教育と普及を行う国内最大の団体です。
AEAJ資格の強みは、次の3点に集約されます。
- 公的性と透明性:公益社団法人として、営利目的ではなく教育・社会貢献を目的に運営
- 統一された学習体系:全国の認定校・教材が共通基準で運用され、内容の信頼性が高い
- 社会的評価:医療・教育・福祉など多様な現場で通用し、履歴書にも記載できる資格
このようにAEAJの検定・資格は、他団体とは異なり「学術的根拠」と「公益性」を兼ね備えた体系的資格です。
混同されやすいアロマ資格(JAA・IFAなど)との違い
JAAやIFAなどの団体もアロマ教育を行っていますが、目的と対象層に違いがあります。
ここでは代表的な団体とAEAJを比較します。
| 団体名 | 主な特徴 | 学習・活動の目的 |
|---|---|---|
| AEAJ(日本アロマ環境協会) | 公益社団法人。正しい知識の普及と環境調和を重視。 | 一般生活から専門分野まで幅広く活用。国内で最も普及。 |
| JAA(日本アロマコーディネーター協会) | 民間団体。感性や表現・サロン運営に重点。 | アロマの感覚的活用・コミュニケーション重視。 |
| IFA(英国国際アロマセラピスト連盟) | 海外団体。実技・臨床重視の国際基準資格。 | セラピストとして国際的に活動。 |
AEAJは、誰でも安心して学べるようにカリキュラムが標準化されており、初心者〜専門職まで対応できる柔軟性を持っています。
一方、JAAやIFAは専門性や活動範囲が特化しており、目的に応じて選択される傾向があります。
公益社団法人資格としての安心感と社会的評価
AEAJ資格が他団体と最も異なる点は、「公益社団法人」ならではの社会的信頼と持続的な教育体制にあります。
公益法人は行政の監督を受けており、運営や資格制度に透明性が求められます。
AEAJ資格の社会的評価ポイント:
- 行政・教育機関・医療福祉分野での認知度が高い
- 全国125校以上の認定スクール・81ブランドの認定精油による統一基準
- 資格取得者数50万人超の国内最大規模
- 環境福祉学会やIFAなど、学術・国際団体との連携実績も豊富
これによりAEAJ資格は、信頼できる知識を持つ証として社会的にも評価されており、アロマを学ぶ上で「最も公的性の高い資格体系」として位置づけられています。
まとめ|アロマテラピー検定1級・2級はアロマの基礎を身につける最初の一歩

アロマテラピー検定1級・2級は、香りを安全に、そして効果的に活用するための基礎知識を身につけられる資格です。
AEAJ(日本アロマ環境協会)が運営する公益性の高い検定であり、初心者から専門職まで幅広い層に信頼されています。
香りの特性や心身への作用を理解することで、日常のセルフケアや家族の健康づくりにも活かせます。
また、合格後にはアロマテラピーアドバイザーなど、次のステップへとつながる発展的な学びも用意されています。
アロマをもっと深く学びたい方や、生活や仕事に役立てたい方にとって、アロマテラピー検定は香りの世界への第一歩となる資格です。
監修者

谷口 順彦
特定非営利活動法人日本統合医学協会理事
総合学園JOTアカデミー理事長
\この記事をお読みの方におすすめの資格!/

心と体の状態に合わせた精油のブレンディングなど、メディカルアロマの活用法を教授できる能力を認定する資格です。
メディカルアロマのスペシャリストとして、精油の専門知識だけでなく基礎医学や心理学など幅広い知識を習得し、目的に合わせた利用法を指導できる専門人材になることを目的にしています。
医療や福祉の現場でアロマセラピーの知識と技術を活かすことを目指します。精油が心身に及ぼす効果を深く学び、対象者や目的に応じた適切なアロマの使用法を身に付けることで、医療現場での代替療法や疾病予防、健康増進に役立てられます。クリニカルアロマセラピーは、西洋医学の補完的な役割を担い、統合医療としても注目されています。
身体の仕組みや心理学、ハーブの知識を基に、アロマが心と体に与える影響を理解することを目指します。精油の特性を学び、医学的視点でのアロマセラピーを通じて、不調に対応するトリートメント技術を習得します。
医療現場でも活用できる高度な知識と技術を持ったセラピストを育成します。