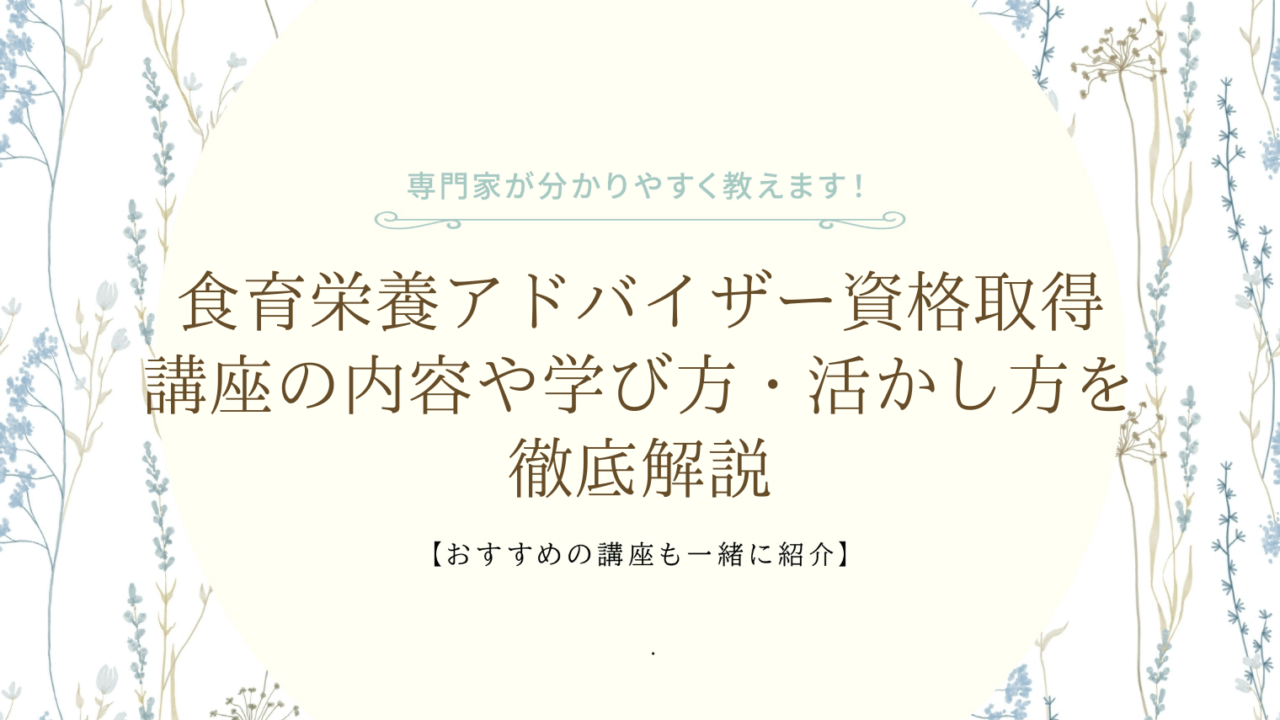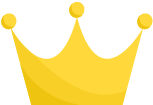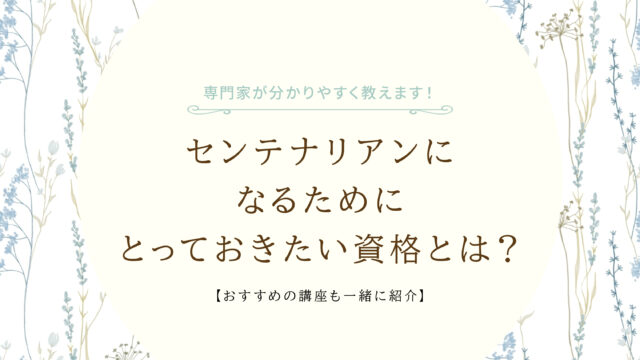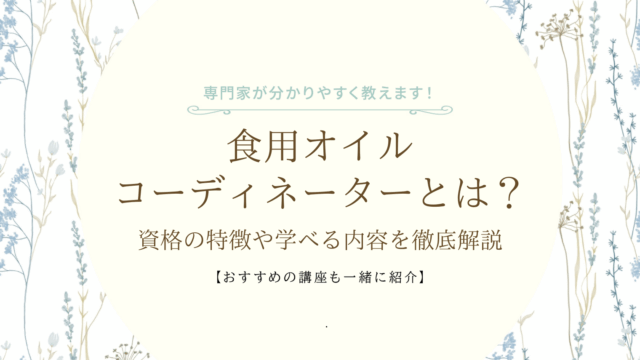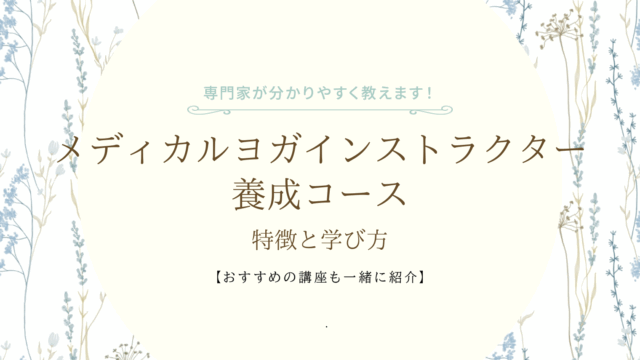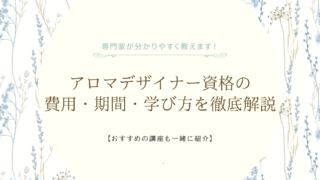「食育栄養アドバイザー資格取得講座」は、栄養学や食育の正しい知識を体系的に学べる日本統合医学協会の認定資格です。
家庭の食生活改善から教育・福祉現場での実践、さらには地域活動や情報発信まで幅広く活かせる点が特徴です。
本記事では、食育栄養アドバイザーの学べる内容、費用、資格の活かし方や他資格との違いを徹底解説します。
食資格は多くの種類が存在します。
この記事では特定非営利活動法人の日本統合医学協会が認定している「食育栄養アドバイザー資格」について解説しています。
\この記事をお読みの方におすすめの資格!/

食育と栄養学の基礎を学び、日々の食生活を通して健康をサポートする力を身につけます。乳児から高齢者まで、ライフステージごとに異なる栄養の重要性やバランスのとれた食事の方法、ダイエットや免疫力向上を目指した食べ方を紹介。
生活習慣病の予防や健康維持に必要な知識も学べます。家族や周囲の人の健康を支えるために、理論と実践を組み合わせた実践的な講座です。
学んですぐに実践できるセンテナリアンの食事の基本の軸を学び、日々の食事の見直すことで、①料理時間の短縮②栄養のバランスが取れる③食材・食費の無駄が減るといったことが目指せます。
また、季節ごとの具体的な献立もご紹介。学んですぐに実践いただけます。
「人生100年時代」を生きる、支えるための生活習慣・介護・社会とのかかわり方など、健康面以外の知識も含め、総括的に学べます。介護士などの福祉関係者や看護師などの医療従事者の方など、高齢者とのかかわりの多い方に多く受講されています。
合格者は非営利活動法人日本統合医学協会のセンテナリアンアドバイザー資格が認定されます。
食育栄養アドバイザーとは?

食育栄養アドバイザーは、食と健康の基礎を体系的に学び、日常生活や教育・福祉の現場で実践できる力を身につけられる資格です。
栄養バランスの取り方や生活習慣病予防などを幅広く学べるため、家庭での子どもの成長サポートから地域活動まで活用範囲が広いのが特徴です。
日本統合医学協会が発行する資格の概要
この資格は、特定非営利活動法人日本統合医学協会が公式に認定する民間資格です。
受講はオンライン形式で、教材学習と修了試験を通じて知識を定着させます。
国家資格の管理栄養士とは異なり、専門職以外の一般の方でも無理なく取得でき、生活に密着した実践的知識の習得を目的としています。
食育の基本理念と学ぶ意義
食育の基本理念は、単に栄養を摂取する知識にとどまらず、食を通じて心身の健全な成長や健康的な生活習慣を育むことにあります。
偏食や生活習慣病のリスクが高まる現代社会において、正しい食の理解は家庭・学校・地域のすべてで必要とされています。
食育栄養アドバイザー資格を学ぶことで、栄養学の知識に加え、日々の食選びを根拠を持って実践できる力が養われ、家族や周囲に対して健康的なライフスタイルを広める役割を担うことができます。
他団体の類似資格との違い
「食育栄養アドバイザー」という名称は複数の民間団体で使われており、内容や目的が異なる場合があります。
例えば、一般社団法人や民間スクールが発行する資格では、食育全般の啓発や料理実習を中心とするケースも見られます。
一方、日本統合医学協会の講座は、医学的根拠に基づいた栄養学と生活習慣病予防に重点を置き、家庭や教育・福祉現場での実践活用を目的としています。
資格取得を検討する際は、発行団体やカリキュラムの特徴を確認し、混同しないことが重要です。
どんな人におすすめの資格か
食育栄養アドバイザー資格は、家庭の食生活を整えたい保護者や、子どもの成長にあわせた栄養管理を学びたい方に特におすすめです。
また、介護や福祉、教育の現場で食を通じた健康づくりを支援したい人にも役立ちます。
さらに、健康志向が高まりつつある中で、正しい食の知識を身につけて情報発信や地域活動に活かしたい方にも適しています。
専門知識がなくても基礎から学べるため、食と健康に関心がある幅広い層に開かれた資格です。
講座で学べる内容

食育栄養アドバイザー講座では、栄養学の基礎から家庭や社会での実践方法まで、幅広い知識を体系的に学べます。
五大栄養素の働きや食習慣と健康との関係、生活習慣病予防に役立つ食事の工夫などを具体的に理解できるのが特長です。
また、子どもの発育や高齢者の健康維持など、ライフステージごとの食の在り方も学習します。
学んだ内容は、家庭の健康管理だけでなく、教育や福祉の現場、さらには地域活動にも応用できる実践的なものです。
栄養学の基礎(五大栄養素・発育期に必要な栄養など)
食育栄養アドバイザー講座では、まず五大栄養素(炭水化物・脂質・たんぱく質・ビタミン・ミネラル)の働きを基礎から学びます。
これらは体を動かすエネルギー源であり、成長や体調維持に欠かせません。
特に発育期の子どもには、骨や筋肉の発達を助けるたんぱく質やカルシウム、免疫を支えるビタミン類が重要です。
栄養素の役割を正しく理解することで、世代ごとに必要な食事を考えられるようになり、家庭や教育現場での実践につながります。
食育と生活習慣病予防
食育は、将来の生活習慣病を防ぐ基盤づくりにも直結します。
肥満や糖尿病、高血圧といった病気は食生活の乱れと深く関係しており、正しい知識を身につけることで早期から予防が可能です。
講座では、栄養バランスの整った献立の工夫や、塩分・脂質・糖分の摂り過ぎを防ぐ方法を学びます。
さらに、年代やライフスタイルに応じた食のアドバイスも理解できるため、家庭だけでなく教育や地域活動においても健康寿命の延伸に役立てることができます。
家庭での実践(子どもの偏食・健康管理)
家庭における食育の実践は、子どもの健やかな成長を支えるうえで欠かせません。
講座では、野菜嫌いなどの偏食への対処法や、成長期に必要な栄養素を取り入れる工夫を学びます。
また、朝食の重要性や間食の選び方、家族全体で取り組める献立づくりなど、日常生活にすぐ活かせる内容が盛り込まれています。
知識を身につけることで「食べさせ方の不安」や「献立のマンネリ化」を解消でき、家族の健康管理に役立つ実践力が養われます。
社会での活用(教育現場・福祉・地域活動)
食育栄養アドバイザー資格で得た知識は、家庭だけでなく社会のさまざまな場面で活かせます。
教育現場では、子どもたちに正しい食の理解を促す授業や講話に役立ち、福祉や介護の分野では高齢者の健康維持や栄養改善に貢献できます。
さらに、地域活動やイベントを通じて食の啓発を行うことで、世代を超えた健康づくりを支援することも可能です。
学んだ知識を共有することで、家庭を超えて地域全体の健康促進に寄与できるのが大きな特徴です。
学び方とカリキュラムの特徴

食育栄養アドバイザー講座は、ライフスタイルに合わせて学べる通信教育形式が大きな特長です。
動画教材やテキストを用いて基礎から応用まで段階的に学習でき、専門知識がない初心者でも取り組みやすい内容になっています。
学習期間はおおよそ3か月が目安ですが、自分のペースで進められるため、忙しい子育て世代や社会人でも無理なく継続可能です。
修了後は認定試験を受け、合格することで資格取得につながる実践的なカリキュラムが整っています。
オンラインで学べる仕組み(動画・テキスト教材)
本講座はすべてオンライン対応で、自宅にいながら体系的に学習できるのが特徴です。
テキスト教材で基礎知識を整理しつつ、動画教材では実践的な解説や図解で理解を深められます。
スマートフォンやパソコンからいつでもアクセスできるため、仕事や家事の合間などスキマ時間を有効に活用可能です。
また、繰り返し視聴できるため、自分の理解度に応じて復習や確認ができ、学びを確実に定着させられる柔軟な学習環境が整っています。
学習期間と学習ペース
食育栄養アドバイザー講座の標準学習期間は約3か月ですが、受講者の生活リズムに合わせて自由に進められます。
集中して学べば短期間での修了も可能ですし、子育てや仕事と両立しながら半年以上かけてじっくり取り組むこともできます。
課題や確認テストを通じて理解度をチェックできるため、知識が定着しやすい設計になっています。
自分のペースで無理なく学べるため、初めて栄養学を学ぶ方でも安心して取り組めるのが大きな魅力です。
試験方法と資格取得までの流れ
食育栄養アドバイザー資格は、受講修了後に行われる在宅試験によって判定されます。
試験は講座内容から出題され、その場で結果が確認できる仕組みです。
合格者は資格申請と入会手続きを行うことで、特定非営利活動法人日本統合医学協会より正式な認定証が発行されます。
学習から試験、資格取得までがすべて自宅で完結するため、忙しい方でも安心して挑戦できるのが大きな魅力です。
受講料と費用の目安

食育栄養アドバイザー講座の受講料には、教材費と1回分の試験料が含まれており、追加の受験費用や認定証発行費用は不要です。
合格後は、日本統合医学協会の認定資格として正式に登録されるため、入会手続きが必須となり、年会費が必要になりますが費用体系がシンプルでわかりやすく、専門学校などに比べて経済的に学べる点が特徴です。
資格取得から継続的な活動まで、安心して取り組める仕組みが整っています。
講座受講料と教材費
食育栄養アドバイザー講座の受講料は、一般受講料39,600円(税込43,560円)が基本です。
条件を満たす方は、モニター受講料19,800円(税込21,780円)で受講することも可能です。
モニター受講ではレポート課題(400字以上)と受講後アンケートの提出が必須となります。
受講料には教材費が含まれており、テキストや動画教材を追加購入する必要がないため、費用が明確で安心して学習を始められます。
資格試験料や認定証の費用
資格試験は受講期間内の好きなタイミングで受験でき、1回分の試験料は受講料に含まれています。
そのため追加費用の心配はなく、自分のペースで資格取得を目指せます。
合格後はその場で結果を確認でき、資格申請と入会手続きを行うことで、日本統合医学協会より認定証が発行されます。
認定証の発行費用は不要ですが、協会への入会が必須であり、年会費7,000円が必要です。
費用体系が明確で安心して取り組めるのが特長です。
食育栄養アドバイザー資格の活かし方

食育栄養アドバイザー資格で得た知識は、家庭や教育現場、福祉分野、さらには地域や発信活動など幅広く活かせます。
子どもの健やかな成長を支える家庭での実践はもちろん、高齢者や地域住民への健康支援にも役立ちます。
さらに、学んだ内容をSNSや講座活動を通じて発信することで、情報提供や副業としての展開も可能です。
生活の質を高めつつ、社会貢献にもつながる資格として、多方面で活用できるのが大きな特徴です。
家庭での活かし方(子育て・家族の健康管理)
食育栄養アドバイザーの知識は、日々の食卓づくりに直結します。
子どもの発育に必要な栄養素を意識した献立作成や、偏食への工夫、季節に合わせた体調管理など、家庭の健康を支える力になります。
また、家族のライフステージごとの栄養ニーズに応じて食生活を調整できるため、生活習慣病の予防や健康維持にも効果的です。
家族みんなが安心して食を楽しめる環境づくりに役立ち、日常の小さな積み重ねが将来の健康につながります。
教育や福祉の現場での活用
食育栄養アドバイザー資格は、学校や保育施設、介護・福祉現場など幅広い分野で役立ちます。
教育の場では、子どもに正しい食習慣を伝える授業や食育イベントに活かせます。
福祉や介護では、高齢者の栄養管理や健康維持をサポートする知識として重宝されます。
また、地域活動やボランティアに取り入れることで、世代を超えて健康意識を高める機会を提供できるのも魅力です。
専門的な立場で食の大切さを伝える力が養える資格です。
発信活動や副業への展開(SNS・地域活動)
食育栄養アドバイザーで得た知識は、発信活動や副業にも活かせます。
SNSやブログを通じて食育や栄養の情報を発信すれば、同じ悩みを持つ人々の参考となり、フォロワーとの信頼関係づくりにもつながります。
また、地域での講座開催やワークショップを通じて、家庭や学校では伝えきれない食の大切さを広める活動も可能です。
資格を持つことで発信の説得力が高まり、ライターや講師など副業のチャンスにも発展できるのが魅力です。
他の食・生活系資格との違い

食育栄養アドバイザー資格は、家庭から教育・福祉まで幅広く活かせる点が特徴ですが、日本統合医学協会には他にも食や生活に関連する資格が複数あります。
それぞれ学べる内容や対象者に違いがあるため、目的に応じて最適な資格を選ぶことが大切です。
以下の表で代表的な資格を比較しました。
| 資格名 | 学べる内容 | 主な対象者 | 活かせる分野 |
| 食育栄養アドバイザー | 栄養学の基礎、生活習慣病予防、家庭や教育現場での食育 | 子育て世代、教育・福祉関係者 | 家庭、教育、福祉、地域活動 |
| アスリート食生活マイスター | スポーツ栄養学の基礎、目的別食事法(疲労回復・筋力アップなど) | アスリート本人、保護者、指導者、スポーツ関係者 | スポーツ現場、教育、家庭、地域活動 |
| 発酵食美インストラクター | 発酵食品の基礎知識とレシピ、免疫力向上 | 発酵食に関心のある方、美容・健康志向の方 | 家庭、料理教室、発酵食指導 |
| 食生活健康長寿アドバイザー | 高齢期の食生活と栄養管理、健康寿命延伸 | 高齢者の家族、介護職、健康づくりに関心のある方 | 介護・福祉、高齢者施設、家庭 |
| 食用オイルコーディネーター | 各種オイルの特性と使い分け、健康効果 | 料理や美容に関心のある方 | 家庭、料理、美容関連 |
| 薬膳インストラクター | 薬膳の基礎、体質改善、季節の食養生 | 健康維持を目的とする方、料理や医療に携わる方 | 家庭、飲食、健康指導 |
食育栄養アドバイザーは、家庭や教育・福祉など幅広い実生活に直結する点で汎用性が高い資格です。
一方で、発酵食や薬膳、オイルなどは専門性に特化しているため、目的や活用シーンに合わせて選ぶと効果的です。
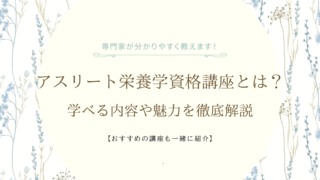
受講を検討している方へのQ&A
食育栄養アドバイザー資格に関心を持った方から多く寄せられる質問をまとめました。
資格取得にあたっての不安や疑問を解消し、自分に合った学びかどうかを判断する参考にしてください。
難易度や学習の進め方、他資格との違い、初心者への適性など、受講前に知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。
受講を検討している方にとって安心材料となり、学習のイメージをより具体的に描けるようになるでしょう。
難易度や合格率は?
食育栄養アドバイザー資格は、初心者でも取り組みやすい内容で構成されています。
栄養学や食育の基礎から段階的に学べるため、専門的な予備知識がなくても安心です。
試験は講座で学んだ内容を理解していれば十分に対応できるレベルで、難解な専門問題は出題されません。
そのため合格率は高く、多くの受講者が無理なく資格を取得しています。
努力次第で誰でも合格を目指せる実用的な資格として、多方面で活用されています。
管理栄養士や食生活アドバイザーとの違いは?
管理栄養士は国家資格であり、病院や学校などで栄養指導や給食管理を行う専門職です。
一方、食生活アドバイザーは広く食生活全般を対象とする民間資格で、検定形式での取得となります。
食育栄養アドバイザーは、日本統合医学協会が発行する資格で、家庭や教育・福祉の現場で活かしやすい点が特徴です。
専門職を目指すためではなく、日常生活や地域活動に直結した知識を得たい方に適しており、資格の目的や活用範囲に違いがあります。
初心者でも学べる?
食育栄養アドバイザー資格は、栄養学や食育を初めて学ぶ方にもわかりやすいよう設計されています。
カリキュラムは五大栄養素や生活習慣病予防などの基礎から始まり、家庭や社会での実践方法まで段階的に学べる構成です。
教材も専門用語をかみ砕いて解説しているため、予備知識がなくても安心です。
動画とテキストを併用する学習形式なので、自分のペースで理解を深められ、忙しい方でも無理なく取り組める点が大きな魅力です。
まとめ|食育栄養アドバイザー資格で家庭と社会に役立つ知識を

食育栄養アドバイザー資格は、栄養学や食育の基礎を学び、家庭・教育・福祉など幅広い場面で実践できる知識を身につけられる資格です。
専門職を目指すためだけでなく、子育てや家族の健康管理、地域での活動や情報発信にも役立ちます。
オンラインで学べる柔軟なカリキュラムと明確な費用体系により、初心者でも安心して取り組める点が魅力です。
学んだ知識を実生活に結びつけることで、自分自身や周囲の健康づくりに大きく貢献できるでしょう。
学びを実生活につなげる方法
学んだ知識を形だけで終わらせず、日々の行動に落とし込むことが大切です。
たとえば、献立を考えるときに五大栄養素を意識する、買い物の際に食品表示を見て選ぶ、家族の体調に合わせて食材を工夫するなど、すぐに実践できる方法があります。
また、学校や地域での食育活動に参加したり、SNSで情報を発信することで、学びを社会へ広げることも可能です。
こうした小さな実践の積み重ねが、資格取得の価値を最大限に活かすことにつながります。
監修者

谷口 順彦
特定非営利活動法人日本統合医学協会理事
総合学園JOTアカデミー理事長
\この記事をお読みの方におすすめの資格!/

食育と栄養学の基礎を学び、日々の食生活を通して健康をサポートする力を身につけます。乳児から高齢者まで、ライフステージごとに異なる栄養の重要性やバランスのとれた食事の方法、ダイエットや免疫力向上を目指した食べ方を紹介。
生活習慣病の予防や健康維持に必要な知識も学べます。家族や周囲の人の健康を支えるために、理論と実践を組み合わせた実践的な講座です。
学んですぐに実践できるセンテナリアンの食事の基本の軸を学び、日々の食事の見直すことで、①料理時間の短縮②栄養のバランスが取れる③食材・食費の無駄が減るといったことが目指せます。
また、季節ごとの具体的な献立もご紹介。学んですぐに実践いただけます。
「人生100年時代」を生きる、支えるための生活習慣・介護・社会とのかかわり方など、健康面以外の知識も含め、総括的に学べます。介護士などの福祉関係者や看護師などの医療従事者の方など、高齢者とのかかわりの多い方に多く受講されています。
合格者は非営利活動法人日本統合医学協会のセンテナリアンアドバイザー資格が認定されます。